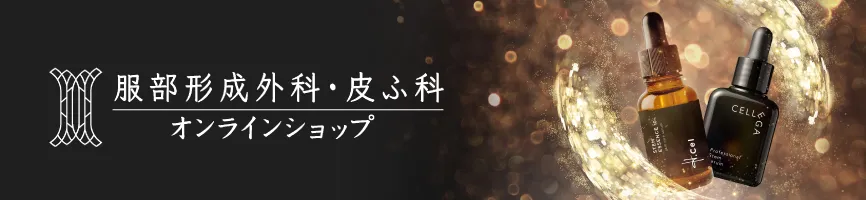長年の経験と実績を持つあざ治療をはじめ、
皮ふ科・外科の治療を保険適用内で行います。
よくご相談をいただく症例
-

あざ治療 青あざ、茶あざ、赤あざ、黒あざなど、あらゆるあざに対応いたします。
-

眼瞼下垂 眼瞼下垂とは、黒目がまぶたで大きく隠れてしまっている状態です。
-

ニキビ/ニキビ跡 白ニキビ、赤ニキビ、炎症性ニキビから、色素沈着や凹みなどのニキビ跡まで、あらゆるニキビのお悩みに対応いたします。
-

赤ら顔/しゅさ 顔(特に鼻や頬)が慢性的に赤くなる皮膚の病気です。毛細血管の拡張や炎症が原因で、ほてりやニキビのような発疹を伴うこともあります。
-

アトピー性皮膚炎 皮膚の状態にあわせて、軟膏治療、内服治療、生活指導など多角的な治療法をご提案します。
-

白癬 水虫(白癬菌)は皮膚糸状菌という真菌(カビ)によって生じる感染症です。
-

陥入爪 陥入爪(かんにゅうそう)とは、爪の端が皮膚に食い込み、炎症や痛みを引き起こす状態です。特に足の親指に多く見られます。
-

湿疹 かゆみを伴う急性湿疹から、繰り返す慢性湿疹など、さまざまな湿疹のお悩みに対応いたします。
その他
-
アレルギー
-
尋常性疣贅 (いぼ)
-
伝染性軟属腫 (水いぼ)
-
蕁麻疹
-
できもの
-
円形脱毛症
-
尋常性乾癬
-
脂漏性皮膚炎
-
脂漏性角化症
-
白斑
-
熱傷
-
べんち・鶏眼
-
ヘルペス
-
帯状疱疹
-
外傷
-
掌蹠膿疱症
-
花粉症
-
ほくろ
-
とびひ (伝染性膿痂疹)
-
稗粒腫
-
多汗症
皮膚のできもの(皮膚腫瘍)
「これ、何だろう?」と思ったら、まずは形成外科へ
皮膚にできたしこり・ふくらみ・イボ・できものなどは、見た目では良性か悪性かを判断するのが難しい場合があります。
「急に大きくなってきた」「痛みや出血がある」「色が変わってきた」「ずっと同じ場所にある」など、気になる皮膚の変化がある場合は、早めの受診をおすすめします。
形成外科では、こんな“できもの”を診察・治療します
- 粉瘤(アテローム)
- 脂肪腫
- 皮膚線維腫
- 老人性疣贅(いわゆる“年寄りいぼ”)
- ホクロ(色素性母斑)
- 血管腫
- 皮膚がん(基底細胞がん、有棘細胞がん、悪性黒色腫 など)
形成外科だからできる、見た目と機能に配慮した治療
形成外科では、皮膚の切開・縫合・再建を専門とする医師が診療を行います。
顔や首など見た目が気になる部位や、傷あとが残りやすい場所でも、できるだけ目立たないような切除・縫合法を選択します。
また、必要に応じて病理検査(組織検査)を行い、良性か悪性かを正確に診断します。
保険診療/自費診療
- 悪性の疑いがある、または生活に支障をきたすものは保険診療の対象です。
- 見た目を整える目的での小さなできもの除去などは自費診療になる場合がありますが、診察時に丁寧にご説明いたします。
「これ、放っておいて大丈夫かな?」と思うできものがあれば、お早めにご相談ください。
形成外科専門医が、見た目と安全性の両方に配慮しながら、的確に診断・治療いたします。
脂漏性皮膚炎(しろうせいひふえん)
頭皮や顔面など皮脂の分泌が盛んな部位(脂漏部位)に生じる湿疹の一種です。
赤ちゃん(新生児~乳児期)から大人(思春期以降)まで発症し、乳児期にみられるものは「乳児型」、思春期以降にみられるものは「成人型」に分類されます。
乳児型の脂漏性皮膚炎は一過性が多く、成人型は良くなったり悪くなったりを繰り返して慢性化しやすく、放置して自然に治ることは少ないため症状が出たら皮膚科での治療が勧められます。
原因と悪化因子
脂漏性皮膚炎の直接的な原因はまだ完全には解明されていませんが、皮膚に常在するマラセチアというカビ(真菌)が大きく関与していると考えられています。
マラセチアは皮脂を栄養に増殖し、その際に皮脂中のトリグリセリドを分解して生じる遊離脂肪酸が皮膚を刺激し炎症を引き起こすことが原因の一つとされています。
皮脂の成分や分泌量の変化(季節や環境の影響)、ビタミンB2・B6の代謝異常、不十分な洗顔・洗髪、過度のストレスや寝不足、ホルモンバランスの乱れなど様々な要因が関連するといわれます。
特に成人型では、皮脂の分泌を促す男性ホルモン(アンドロゲン)の影響で男性に発症しやすい傾向があります。
また乾燥した環境や過労・ストレス、偏った食生活によるビタミンB群不足なども症状を悪化させる要因とされています。
これら複数の要因が重なり合って皮膚のバリア機能が乱れ、結果的に脂漏性皮膚炎を発症・悪化させると考えられます。
治療法
脂漏性皮膚炎の治療は、皮膚の炎症を抑え真菌への対策を行い、再発を防ぐことが目標です。
外用薬(ぬり薬):
炎症を抑えるためにステロイド(副腎皮質ホルモン)外用薬を使用するのが基本です。同時に、原因とされるマラセチア菌の増殖を抑える抗真菌薬(抗カビ剤)を含む塗り薬やローションを症状に応じて併用します。頭皮の症状にはクリームよりも塗りやすいローションタイプの外用薬が処方されることが多いです。症状が落ち着いてきたら抗真菌薬のみをしばらく続けるなど、医師の指示のもと段階的に治療を行います。なお乳児の脂漏性皮膚炎では、炎症が強い場合にごく弱いステロイド軟膏を短期間塗ることもありますが、基本的には石けんできれいに洗浄し保湿するケアで自然に良くなるケースがほとんどです。
シャンプーによるケア:
頭皮の脂漏性皮膚炎では、薬用シャンプーを用いたケアも有効です。具体的には、低刺激性で余分な皮脂をしっかり落とせるシャンプーや、抗真菌成分(ミコナゾール、ケトコナゾールなど)を含むシャンプーを使用するとフケや炎症の改善に役立ちます。赤ちゃんの場合もベビー用シャンプーでやさしく洗髪し、頭皮にこびりついたフケは入浴前にベビーオイルなどでふやかしてから洗い流すといったケアを行います。
熱傷(やけど)
熱傷は、高温の物質や液体、蒸気などによって皮膚組織が損傷を受ける状態です。
損傷の深さ(深度)によって、Ⅰ度・Ⅱ度・Ⅲ度の3段階に分類されます。
熱傷の深度は、熱源の温度や接触時間によって変わりますが、受傷直後には正確な診断が難しいことが多く、時間の経過とともに深度が進行する場合もあるため、注意が必要です。
熱傷の分類
Ⅰ度熱傷:
皮膚が赤くなり(紅斑)、ヒリヒリした痛みと軽度のむくみ(浮腫)が見られます。表皮のみに損傷がとどまり、通常は跡を残さずに治癒します。
Ⅱ度熱傷:
初期には強い熱感を伴う赤みが見られ、数時間以内に水疱やびらん(皮がむけるような状態)を形成します。表皮の下にある真皮まで損傷が及ぶことがあります。
Ⅲ度熱傷:
皮膚の全層、あるいはそれ以上の深さにわたって損傷を受け、痛みを感じにくいこともあります。傷跡が残る可能性が高く、外科的治療が必要になる場合があります。
治療
熱傷の治療は、損傷の深さや広がり、部位によって異なります。
軽度のやけどであっても、適切な初期対応が治癒や傷跡の残り方に大きく影響するため、早めの受診をおすすめします。
当院では、日本熱傷学会認定の熱傷専門医である院長が診察・治療を担当いたします。
やけどに関するお悩みやご不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
鶏眼(けいがん)
別名:「うおのめ」
鶏眼は、物理的な圧迫や摩擦により、限局的に角質が厚く(過角化)なる状態で、特に足底に好発します。靴が合わない、歩き方の癖、足の変形などが原因となることが多く見られます。
肥厚した角質の中心が芯のように真皮層へ向かって入り込むため、魚の目のような外観を呈し、痛みを伴うこともあります。
治療には、スピール膏などの角質を軟化させる貼付薬が用いられるほか、圧迫の原因除去(インソールや靴の見直しなど)も重要です。
再発を防ぐためには、原因となる物理的刺激を避けることが大切です。
ご自身で無理に削ったりすると感染の原因になることがあるため、自己処理にはご注意ください。お困りの場合は、皮膚科での専門的な処置をおすすめします。
胼胝(べんち)
胼胝は、繰り返される圧迫や摩擦によって、皮膚の角質が限局的に肥厚した状態です。
鶏眼(うおのめ)と同様の原因で生じますが、芯を持たないため痛みが少ないのが特徴です。
特に、手のひらや足底、骨の突出している部位に好発し、歩行や作業によってさらに悪化することがあります。
治療には、肥厚した角質を削る処置が最も効果的で、当院でも丁寧に行っております。
また、再発を防ぐためには、圧迫や摩擦を避ける工夫(インソールや靴の見直しなど)も重要です。
ヘルペス(単純ヘルペスウイルス感染症)
ヘルペスは、単純ヘルペスウイルス(HSV)1型または2型の感染によって発症します。
初感染によって症状が現れる場合と、体内に潜伏していたウイルスが再活性化して再発する場合があります。
症状としては、限局的に痛みを伴う小さな水疱(すいほう)が出現し、かゆみやピリピリした違和感を伴うこともあります。
全身のどこにでも発症する可能性がありますが、特に口唇(くちびる)・陰部・手指などに好発します。
初感染時には、発熱やリンパ節の腫れ(リンパ節腫脹)を伴うこともあります。
治療について
症状の程度や発症部位に応じて、抗ウイルス薬の内服または外用を行います。
再発を繰り返す場合には、再発予防のために抗ウイルス薬を継続的に服用する治療(抑制療法)を行うこともあります。
ヘルペスは早期治療が最も効果的です。
「くちびるがムズムズする」「ピリピリする」などの違和感を感じたら、できるだけ早くご相談ください。体を休めることも重要です。
外傷
外傷治療は「形成外科医」へ
見た目と機能、両方に配慮した専門的な治療を行います。
けがをしたとき、ただ縫って終わり。ではなく、「どのように治るか」「傷あとがどのように残るか」まで考えるのが、形成外科の外傷治療です。
形成外科は、皮膚・皮下組織・筋肉などの再建と修復を専門とする診療科です。
切り傷・すり傷・裂傷・やけどなどの外傷はもちろん、顔や手など「見た目の影響が大きい部位」や、「動き・感覚」に関わる部位のケガにも精密に対応します。
一般的な外科・救急との違い
救急や一般外科では「止血し、縫合して、治す」ことが主な目的ですが、
形成外科では「なるべく目立たず、機能も損なわずに治す」ことに重きを置きます。
- 傷あとが残らないように丁寧に縫合
- 将来の成長や表情の動きも見越したデザイン
- 見た目の左右差や凹凸を最小限に抑える工夫
- 必要に応じて特殊な縫合法(真皮縫合、皮膚接着剤など)や形成術を併用
など、「仕上がりの美しさ」と「元の機能に戻すこと」を意識した治療を行います。
当院の特徴
当院では、形成外科専門医が外傷治療を担当しています。
小さなすり傷から、顔の裂傷・指のケガ・やけど・皮膚の欠損まで、年齢や部位を問わず幅広く対応可能です。
「将来を考えて、できるだけきれいに治したい」
「子どもが顔にけがをしてしまって不安」
「大きな傷ではないけど、傷あとが気になる」
そのようなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
初期治療の選択が、傷あとや機能の回復に大きく影響します。
ホクロ(色素性母斑)
ホクロは、母斑細胞が集まってできる良性の皮膚腫瘍です。母斑細胞性母斑とも呼ばれます。
多くは健康に問題ありませんが、形・大きさ・色の変化がある場合は、皮膚がん(悪性黒色腫など)との鑑別が重要になります。
当院での治療方針と保険診療・自費診療の違い
当院では、ダーモスコピーという専用の拡大鏡を使い、ホクロの状態を丁寧に観察し、悪性の可能性があるかどうかを判断します。
保険診療の対象
以下のような場合、保険診療での切除手術が適用されます。
悪性の疑いがある場合(大きさ・形・色の変化など)
出血、痛み、かゆみなどの症状がある場合
衣類や髭剃りなどで繰り返し擦れてしまう部位など。
この場合は、外科的に切除し、病理検査(顕微鏡による組織検査)を行います。
自費診療(自由診療)の対象
以下のような場合は、美容目的の治療と判断され、自費診療となります。
- 「見た目が気になる」「メイクで隠せない」「印象を変えたい」などの審美目的での除去
- 悪性の可能性が低く、機能的な問題がない場合
このようなホクロには、炭酸ガス(CO2)レーザーによる治療が可能です。
レーザーは出血が少なく傷もサイズアップがありません。
ただし、深いホクロは炭酸ガスレーザー後も、残存するため、減量術と考える必要があります。
まずはお気軽にご相談ください
ホクロが気になる・邪魔になる・見た目に影響しているなど感じる方や、
「これってホクロ?がんじゃない?」とご心配な方も、ぜひ一度ご相談ください。
保険・自費いずれの対応も可能です。患者様のご希望と医学的評価の両方をふまえ、最適な治療法をご提案いたします。
とびひ (伝染性膿痂疹)
「とびひ」は、皮膚にできた傷や虫刺されなどから細菌(主に黄色ブドウ球菌や溶連菌)が感染して起こる皮膚の病気です。
正式には「伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん)」といい、特に子どもに多く見られます。
水ぶくれやかさぶたができ、かゆみを伴いながら周囲に広がっていくのが特徴で、引っかいた手を介して別の部位に“飛び火”するように広がることからこの名前がついています。
虫刺され、あせも、湿疹などを掻いたところから細菌が入り込み感染し、赤み、水ぶくれ、じゅくじゅく、かさぶたなどが見られます。強いかゆみがあり、掻くことでより悪化・拡大しやすくなります。
症状に応じて、抗菌薬の内服や塗り薬(抗生物質の外用)を使用します。
また、患部を清潔に保ち、爪を短く切る、手洗いを徹底するなどのケアが大切です。
広がる前にご来院ください。